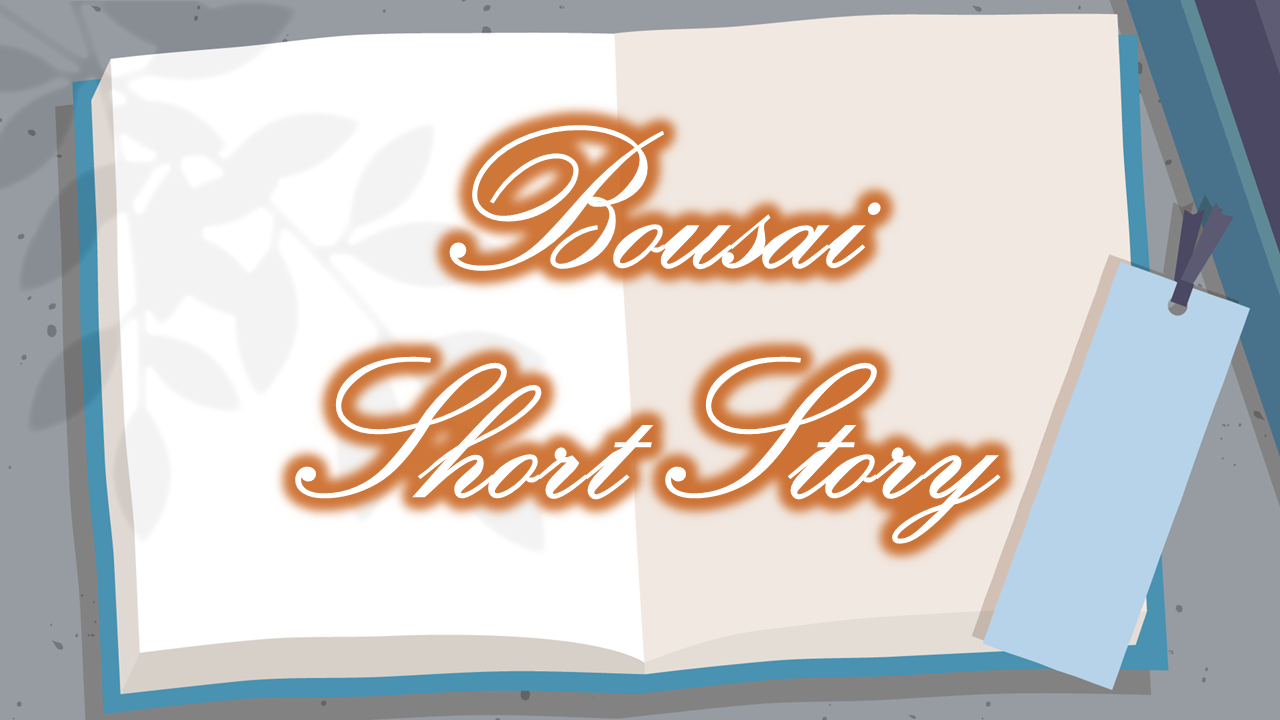
ソロ活防災女子のススメ
小町は会社員で独身の女性だった。
彼女は恋愛に興味がなく、防災に夢中だった。
彼女は自宅に非常用持ち出し袋や防災グッズを常備し、地震や火災などの災害に備えていた。
彼女は毎日、防災情報や防災グッズのレビューをチェックし、自分の防災力を高めることに励んでいた。
ある日、彼女は会社の同僚から飲み会に誘われた。
彼女は断ろうとしたが、上司から強制的に参加させられた。
飲み会では、同僚たちは恋愛話や結婚話で盛り上がっていた。
彼女は興味がなかったが、礼儀をわきまえて相槌を打っていた。
すると、隣に座っていたイケメンの男性が彼女に話しかけてきた。
「小町さん、恋人はいるんですか?」
彼は彼女の同期で、営業部のエースだった。
彼は女性からモテていたが、なぜか彼女に興味を持っていたらしい。
「いえ、いません」
と小町は答えた。
「恋愛よりも防災が大事だと思っています」
「防災?」
「はい。私はソロ活防災女子です。自分の命は自分で守るという信念を持っています」
「ソロ活防災女子?」
「そうです。私は自分の防災力を高めることに情熱を注いでいます。例えば、このバッグには非常用持ち出し袋が入っています。中には水や食料、懐中電灯やラジオ、救急セットや毛布などが入っています。これだけあれば、少なくとも3日間は生き延びることができます」
「すごいですね」
「それだけではありません。私は常に地震や火災などの災害に備えています。このネックレスには笛がついています。これは火災時に煙で声が出せなくなったときに助けを呼ぶためのものです。このブレスレットには火打ち石がついています。これは停電時に火を起こすためのものです。この指輪にはコンパスがついています。これは道に迷ったときに方向を確認するためのものです」
「それもすごいですね」
「ありがとうございます。私は防災グッズを身につけることで安心感を得ています。私は恋愛よりも防災を選んだ生き方に満足しています」
「そうですか」
彼は少し困惑した表情をした。
「でも、恋愛も楽しいですよ。小町さんみたいな素敵な女性なら、きっと素敵な男性と出会えますよ」
「そうでしょうか?私は恋愛に興味がありません」
「そうなんですか?残念ですね」
彼はしばらく沈黙した。
彼は彼女にアプローチしようと思っていたが、彼女の防災への情熱に圧倒されてしまった。
彼は彼女に何を話せばいいのかわからなくなってしまった。
そのとき、突然、地震が起きた。飲み会場は揺れ始めた。
グラスや皿が割れ、テーブルや椅子が倒れた。人々は悲鳴を上げてパニックに陥った。
小町は冷静だった。
彼女はすぐに自分のバッグを持ち、イケメンの男性を引っ張って外に出た。
「早く逃げましょう!」
「え?どこに?」
「安全な場所に!」
彼女は彼を連れて近くの公園に走った。
公園では、他の人々も避難していた。
彼女は彼と一緒に開けた場所に座った。
「大丈夫ですか?怪我はありませんか?」
「いえ、大丈夫です。小町さん、ありがとうございます」
「どういたしまして。私は防災グッズを持っていますから、心配ありません」
彼女は自分のバッグから非常用持ち出し袋を取り出した。
「これが私の非常用持ち出し袋です。中には水や食料、懐中電灯やラジオ、救急セットや毛布などが入っています。これだけあれば、少なくとも3日間は生き延びることができます」
「すごいですね。小町さん、本当に防災に詳しいんですね」
「ありがとうございます。私は防災が好きなんです」
「そうなんですか?それは素晴らしいですね」
彼は彼女の防災への情熱に感心した。
「小町さん、私も防災に興味があります。小町さんに教えてもらえませんか?」
「本当ですか?それは嬉しいですね。私は防災のことを話すのが大好きです」
「そうなんですか?それなら、私も聞くのが大好きです」
彼は彼女の目を見て微笑んだ。
「小町さん、私はあなたが好きです。あなたと一緒に防災を学びたいです」
「え?本当ですか?私もあなたが好きです。あなたと一緒に防災を楽しみたいです」
彼女は彼の手を握って微笑んだ。
「それでは、これから一緒にソロ活防災カップルになりましょう」
「そうしましょう」
二人はキスをした。
おわり
この小説はフィクションです。実在の人物や団体とは関係ありません。
