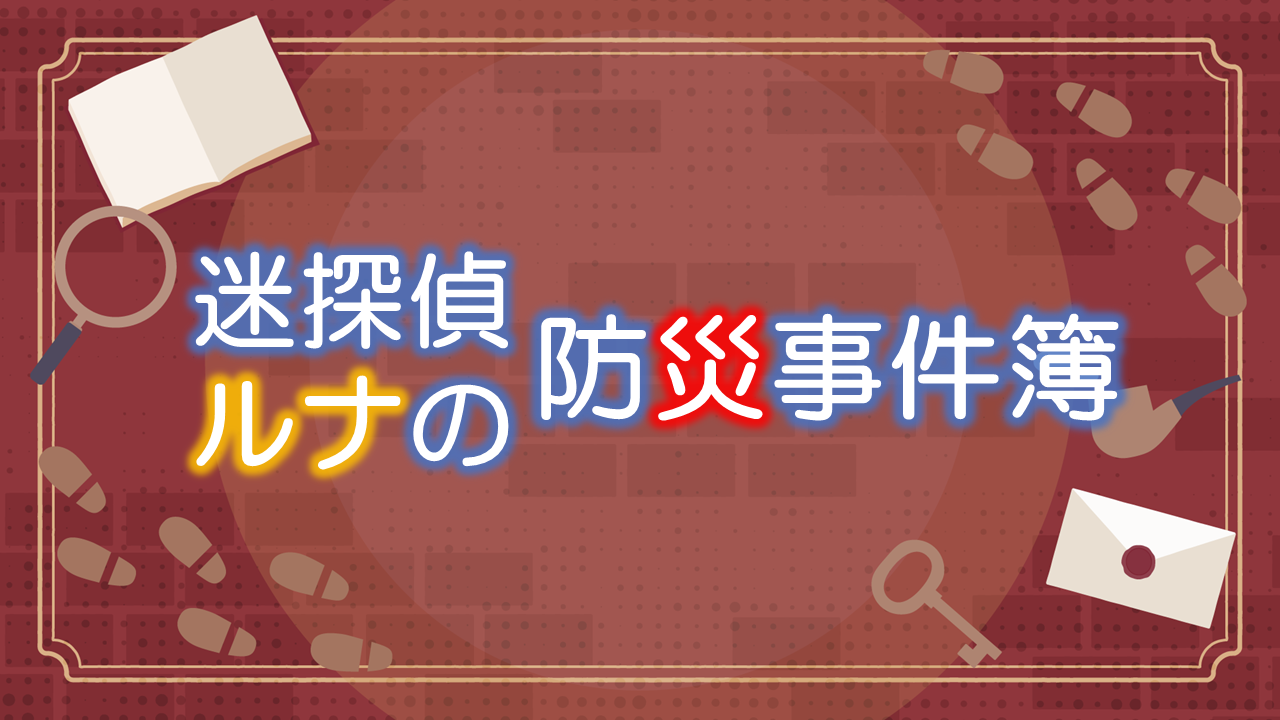
迷探偵ルナの防災事件簿 鳴らない火災報知器
天空ルナ(あまそらるな)は、16歳の女子高生で妄想癖のある防災マニアだった。
彼女は、自分が迷探偵ルナという名の名探偵だと思い込んでいた。
彼女は、防災を積極的に活用して、すべて妄想で事件を解決する特技を持っていた。
彼女には、防災にあまり関心のないユキという親友がいた。
ユキは、ルナの妄想に付き合わされることが多く、苦労していた。
ある日、ルナとユキは、学校の放課後に図書館に行った。
ルナは、新刊の防災本を借りようとしたが、すでに貸し出されていた。
ルナは、がっかりしたが、ユキは、ほっとした。
ルナは、図書館の中を見回した。
すると、彼女は、何かに気づいたようだった。
「ユキ、あそこに見える火災報知器、おかしくない?」
「どこ?ああ、あれか。どうおかしいの?」
「見てごらんよ。火災報知器の下に小さな穴が開いてるよ。それに、火災報知器の色も少し違うような気がする」
「そう?私には普通に見えるけど」
「普通じゃないよ。これは事件だよ。誰かが火災報知器をいじって何か仕掛けたんだよ」
「え?そんなことあるの?」
「あるよ。例えばね、火災報知器の中に爆弾を仕込んだりするとか」
「爆弾!?」
「そうだよ。もしかしたら今にも爆発するかもしれないよ」
「やめてよ、怖いじゃない」
「大丈夫だよ。私が迷探偵ルナだからね。この事件を解決してみせるよ」
「事件じゃないってば」
ルナは、無視して図書館員に近づいた。
「すみません。この火災報知器について教えてください」
「はい。どうされましたか?」
「この火災報知器は最近取り付けられたものですか?それとも以前からありましたか?」
「ええと、この火災報知器は以前からありますよ。何か問題がありましたか?」
「問題がありますよ。この火災報知器は偽物ですよ」
「偽物!?どういうことですか?」
「この火災報知器の下に穴が開いていますよね。それに色も少し違いますよね」
「確かに穴は開いていますね。でも色は普通ですよ」
「普通じゃありませんよ。本物の火災報知器は白色ですが、この火災報知器はクリーム色ですよ」
「クリーム色?そんなことないですよ」
「じゃあ、比べてみましょうか。他の火災報知器と」
ルナは、図書館の中を走り回って、他の火災報知器を探した。
ユキは、困惑しながらついていった。ルナは、やっと見つけた火災報知器を指さした。
「見てください。こちらの火災報知器は白色ですよね。でもあそこにある火災報知器はクリーム色ですよね」
「確かに少し色が違いますね。でもそれがどうしたんですか」
「それがどうしたんですかって、これは明らかに偽物ですよ。本物の火災報知器と偽物の火災報知器を入れ替えたんですよ。そして偽物の火災報知器の中に何か仕掛けたんですよ」
「何を仕掛けたんですか?」
「それはわかりません。でも危険なものだと思いますよ。もしかしたら爆弾だったりするかもしれませんよ」
「爆弾!?」
「そうだよ。だから私たちは早くこの図書館から出ないといけませんよ。そして警察に通報しないといけませんよ」
「本当にそう思うんですか?」
「もちろんだよ。私は迷探偵ルナだからね。妄想で事件を解決する特技があるからね」
「妄想で事件を解決する特技って何ですか?」
「それはね、私の頭の中で事件のシナリオを作り出して、犯人の動機や手口や証拠を推理することだよ」
「それってただの妄想じゃないですか」
「妄想じゃないよ。推理だよ。私は妄想で事件を解決することができるんだよ」
「それってどうやって証明するんですか」
「証明する必要なんてないよ。私は自分の妄想に自信があるからね」
「自信があるだけでいいんですか」
「そうだよ。私は迷探偵ルナだからね」
ルナは、自分の妄想に満足して笑った。ユキは、呆れてため息をついた。
「ルナ、本当に困りますよ。こんなことで図書館を騒がせて、警察に迷惑をかけて、どうするんですか」
「大丈夫だよ。私がすべて解決してみせるよ」
「解決する前に逮捕されるかもしれませんよ」
「逮捕されないよ。私は迷探偵ルナだからね」
ルナは、図書館員に向かって叫んだ。
「早くみなさん、この図書館から出てください!ここに爆弾が仕掛けられています!警察に通報してください!私は迷探偵ルナです!この事件を解決してみせます!」
図書館員は、ルナの言葉に驚いて目を見開いた。
「爆弾!?迷探偵ルナ!?何を言ってるんですか!?」
図書館内は、パニックに陥った。
おわり
この小説はフィクションです。実在の人物や団体とは関係ありません。
